
- 二宮神社
-
1200年前に嵯峨天皇の勅令によって建立された古社で、市の有形文化財。
下総三山の七年祭りで知られる。境内には樹齢300年を超すイチョウが。
二宮神社WEBサイトはこちら



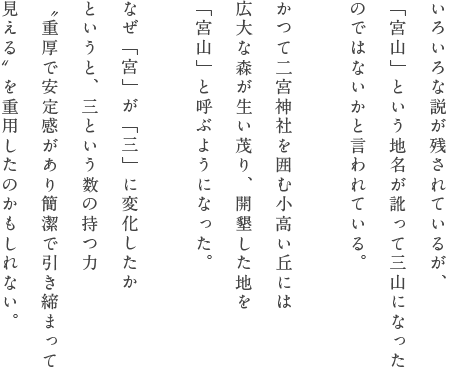

1200年前に嵯峨天皇の勅令によって建立された古社で、市の有形文化財。
下総三山の七年祭りで知られる。境内には樹齢300年を超すイチョウが。
二宮神社WEBサイトはこちら

室町時代、陸奥守康胤の奥方が妊娠11ヶ月の末に男子を出産した奇跡を祝った大祭が起源。県内にある9神社の神輿が威勢良く二宮神社に集結する。

古くは二宮神社の別当で、徳川の家臣・渡辺氏の善提寺だった。
境内には遠い四国まで行かなくとも八十八箇所巡りができる札所がある。

幕末の三山の開墾が進むと、七福神の美女・弁財天が鎮神として迎えられた。
昭和に建立された本殿の中でも今も身長15cmの弁財天像が微笑んでいる。

かつては三山を守る道祖神として堂々と道沿いに並んでいた庚申塔。
7つの塔のうち一つは1727年(江戸中期)に造られ、船橋市最古の遺品である。

江戸時代には幕府の放牧場、明治時代には騎兵連隊の司令部があった馬の町・三山に祀られた馬頭観世。
よく見ると、冠に馬の頭が彫られている。

三山中学校の敷地内にある上面に+が刻まれた謎の石…。
その正体は、国土地理院が測量した際に緯度・経度・標高の基準にした二等三角点だ。

出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)参拝を「奥州参り」と云い、
6年に1回、七年祭りの前年に行われている。
最古の記念碑は文政2年(1819年)である。

戦地で鉄道を敷設する「鉄道連隊」の訓練が行われた。
第二次大戦後、津田沼~松戸間の演習線は新京成電鉄に。津田沼~千葉間の演習線は道路に。

司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」の主人公・秋山好古(あきやま よしふる)が指揮した騎兵連隊はこの地で訓練を重ね、日露戦争で世界最強のロシア騎兵軍団を打破した。

商店街のけやき通りが騎兵連隊の軍用道路だった。
当初の道幅は馬が歩ける14mだったが、戦車が登場すると約21m(十二間)に拡張された。

明治34年、秋山好古が指揮する騎兵連隊が創設され、世界の兵学の研究対象になるほどの躍進を遂げる。駐屯地である三山は一大軍都として栄えた。

大雀命(おおさざきのみこと)、別名・仁徳天皇を祀った神社。
明治時代に二宮神社に合祀(ある神社の祭神を別の神社で合わせて祀る)された。